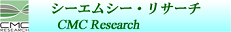サマリー
― 研究、規制、自動化、そして教育へ ―
本書の特徴
-
従来の動物実験に代わる、効率的で精度の高い手法として注目される培養細胞を用いた創薬研究の最新動向を解説!
-
飛躍するMPS/オルガノイド研究、細胞間コミュニケーションの可能性を切り開くエクソソーム研究、iPS細胞技術がもたらした創薬研究の革新など、最先端動向を詳細に解説!
-
新たな局面を迎える実験自動化技術に着目!
-
技術の進展に伴い浮上する、人材育成の課題に問題提起!
-
第一線でご活躍の研究者により最新の知見と展望を紹介!
はじめに
近年のバイオテクノロジー分野における進展は目覚ましく、創薬研究においても、従来の動物実験に代わる、より効率的で精度の高い手法として、培養細胞を用いた研究が注目されています。
2018年5月に出版された「創薬のための細胞利用技術の最新動向と市場」は、多くの研究者の皆様に最新の情報をお届けすることができ、大変好評をいただきました。それから6年、細胞培養技術とその周辺技術はさらに飛躍的な発展を遂げ、創薬研究の現場は新たな局面を迎えています。
本書では、培養細胞を用いた創薬研究の最前線を、以下のテーマに焦点を当てました。
ヒト組織を模倣するMPS/オルガノイド研究の進展:
体性幹細胞、多能性幹細胞を用いたオルガノイドを含むMPSの進歩は、腸管、肝臓、脳、眼球、肺、腎臓といった様々な生体組織をin vitroで再現することを可能にしました。創薬研究における、よりヒトに近い環境での評価を可能にする技術として、その将来性は計り知れません。
細胞間のメッセンジャー、エクソソーム研究の進化:
細胞間コミュニケーションの重要な役割を担うエクソソームは、創薬における新たなターゲットとして、また、ドラッグデリバリーシステムへの応用も期待されています。本書では、エクソソームの多様性、不均一性、そして治療への応用における課題と展望について解説します。
個別化医療を推進するiPS細胞技術:
ヒトiPS細胞から誘導された神経細胞は、創薬スクリーニングや非臨床試験に新たな道を切り拓きました。さらに、疾患特異的iPS細胞を用いることで、患者一人ひとりの病態に合わせた創薬、個別化医療の実現に向けた研究が進んでいます。
創薬研究の効率化を実現する自動化技術:
細胞培養工程の自動化は、創薬研究の効率化、標準化、そしてコスト削減に大きく貢献します。本書では、最新の自動化技術の動向と、今後の創薬研究における役割について考察します。
次世代を担う人材育成の重要性:
これらの技術革新を支え、さらに発展させていくためには、高度な知識と技術を持った人材の育成が不可欠です。本書では、細胞培養技術、GMP教育の現状と課題、そして産学官連携による取り組みについて解説するとともに、VRやシミュレーションゲームといったデジタル技術を活用した教育の可能性についても言及します。
本書が、培養細胞を用いた創薬研究に携わるすべての研究者、そしてこの分野に興味を持つ学生の皆様にとって、最新の知見を得るとともに、今後の研究開発、そして人材育成の指針となることを切に願っております。
ページTOPに戻る
目次
第1編 神経細胞
総括:神経細胞を用いた創薬研究の今 関野祐子
第1章 ヒトiPS細胞由来神経細胞を用いた非臨床試験法の開発への期待と課題 関野祐子,古江美保
1 はじめに
2 安全性薬理試験における新しいインビトロ試験法開発
2.1 医薬品の非臨床試験と規制科学
2.2 安全性薬理試験の改訂の動き
2.3 ヒトiPS細胞を使った新しい試験法の導入例
3 ヒトiPS細胞由来“神経細胞”の創薬ニーズと課題
3.1 ターゲット探索的研究におけるニーズ
3.2 ターゲット探索的研究利用における課題
3.3 非臨床試験におけるニーズ
3.4 非臨床試験利用における課題
3.5 研究データの信頼性確保
3.6 ヒトiPS細胞株の継代,維持,品質保証
3.7 分化誘導法の課題
4 ヒトiPS細胞由来“神経細胞”の次なる展開
4.1 医薬品副作用予測における課題
4.2 高齢者における中枢神経系リスク予測の重要性
4.3 医薬品副作用の学習記憶障害リスク予測
4.4 神経細胞の樹状突起スパインを指標とする試験法開発
4.5 今後の展望
参考文献
第2章 スクリーニングのためのヒトiPS細胞由来神経細胞のシナプス成熟度評価法 福角勇人,金村米博
1 はじめに
2 シナプス成熟のための培養法,分化誘導法の種類と特徴
2.1 ヒトiPS細胞由来神経細胞の2次元培養法
2.2 3次元浮遊培養法(脳オルガノイド)
3 ヒトiPS細胞由来神経細胞のシナプス成熟度評価法
3.1 遺伝子発現解析
3.1.1 RNAシーケンシング(RNA─seq)
3.1.2 定量的RT─PCR法(RT─qPCR法)
3.1.3 RT─PCR法
3.2 タンパク質発現解析
3.2.1 ウエスタンブロット法
3.2.2 細胞免疫染色法
3.3 神経細胞の機能性評価
3.3.1 カルシウムイメージング法
3.3.2 パッチクランプ法
3.3.3 多点電極アレイ(MEA)法
4 おわりに
参考文献
第3章 iPS細胞由来神経細胞を用いたテーラーメイド創薬 森本 悟
1 はじめに
1.1 iPS細胞技術の進展と科学的意義
1.2 テーラーメイド創薬の現状と期待
1.3 創薬分野における市場と技術動向
1.4 今後の課題
2 テーラーメイド創薬におけるiPS細胞の役割
2.1 iPS細胞技術とテーラーメイド創薬
2.2 ヒトiPS細胞疾患モデルを用いたiPS細胞創薬の具体例
2.3 iPS細胞創薬スクリーニングの利点
3 テーラーメイド創薬における患者層別化の重要性
3.1 患者層別化(Stratification)とテーラーメイド創薬の背景
3.2 孤発性患者iPS細胞ライブラリーの役割
3.3 iPS細胞モデルを用いた患者層別化
─ALS(筋萎縮性側索硬化症)におけるテーラーメイド創薬─
4 iPS細胞由来神経系細胞を用いたテーラーメイド創薬とバイオマーカーおよびサロゲートマーカーの開発
4.1 バイオマーカーとサロゲートマーカーの定義と役割
4.2 iPS細胞を用いた臨床的なバイオマーカーとサロゲートマーカーの開発
4.3 細胞外小胞(エクソソームを含む)やAIの活用によるバイオマーカー探索
5 テーラーメイドiPS細胞創薬の展望と課題
6 おわりに
参考文献
第4章 疾患特異的iPS細胞から作製した神経系細胞を用いた病態・創薬研究 河野岳生,小薮直生,近藤孝之,井上治久
1 はじめに
2 iPS細胞の脳神経疾患の創薬研究への応用
3 脳神経疾患特異的iPS細胞を用いた創薬研究
3.1 筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic lateral sclerosis:ALS)
3.2 アルツハイマー病(Alzheimer’s disease:AD)
3.3 パーキンソン病(Parkinson’s disease:PD)
3.4 白質脳症
3.4.1 アレキサンダー病(Alexander disease:AxD)
3.4.2 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症(Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy:CADASIL)
3.4.3 那須・ハコラ病(Nasu-Hakola disease:NHD)
3.4.4 ペリツェウス・メルツバッハ病(Pelizaeus-Merzbacher disease:PMD)
3.4.5 白質消失病(Vanishing white matter disease:VWMD)
3.5 精神疾患
4 iPS細胞を用いた脳神経疾患研究における課題と今後の展望
5 おわりに
謝辞
参考文献
第2編 エクソソーム
総括:エクソソーム 古江美保
第1章 エクソソーム製剤(EV製剤)の品質・安全性評価に関するレギュラトリーサイエンス研究 山元智史,石井明子
1 概要
2 エクソソームとは
3 EV製剤の開発動向
4 EV製剤の品質安全性確保の課題
4.1 EV製剤の品質評価の課題
4.2 EV製剤の有効性・安全性評価の課題と品質特性との関連
4.3 品質リスクマネジメント(QRM:Quality Risk Management)の考えに沿った管理戦略構築
5 EV製剤の開発推進と品質安全性確保に向けたレギュラトリーサイエンス研究
参考文献
第2章 バイオマーカーとしての細胞外小胞の活用 吉岡祐亮
1 細胞外小胞とは
2 細胞外小胞の構成因子
3 疾患と細胞外小胞
4 疾患バイオマーカーとしての細胞外小胞
5 細胞外小胞による細胞の品質管理は可能か?
6 おわりに
参考文献
第3章 エクソソームの粒子径と電荷の分布測定 一木隆範
1 はじめに
2 エクソソームの評価手法
3 粒子径分布の評価
3.1 顕微鏡法
3.2 散乱法
4 ゼータ電位分布の評価
5 マイクロ流路を用いた粒子径・ゼータ電位同時計測システム
5.1 ナノ粒子解析装置の概要
5.2 解析方法
5.3 陰イオン交換カラムを用いて分離したEV試料の測定事例
5.4 形状推定への展開6おわりに
参考文献
第3編 オルガノイド
総括:オルガノイド研究と利用 粂 昭苑
第1章 代謝制御による内胚葉分化とオルガノイド研究への応用 白木伸明,粂昭苑
1 はじめに
2 PSCsの代謝特性
2.1 グルコースとグルタミン
2.2 スレオニン
2.3 メチオニン
2.4 亜鉛
3 代謝特性を利用した内胚葉細胞分化誘導
3.1 特異的な代謝システムを利用した肝臓分化
3.2 グルコース代謝制御による膵臓分化
3.3 アミノ酸代謝制御による膵臓分化
4 メチオニン代謝および亜鉛動態を利用した膵臓分化誘導
5 おわりに
参考文献
第2章 ヒト腸管オルガノイドを用いた医薬開発プラットフォーム 乾 達也,水口裕之
1 腸管薬物動態評価系の現状と課題
2 オルガノイド培養を組み合わせたヒトiPS細胞由来腸管上皮細胞の開発
3 おわりに
参考文献
第3章 ヒト呼吸器オルガノイドを用いた感染症創薬 橋本里菜,高山和雄
1 はじめに
2 呼吸器オルガノイドを用いた新型コロナウイルス感染症研究
2.1 呼吸器オルガノイドを用いたウイルス侵入阻害薬の開発と評価
2.2 呼吸器オルガノイドを用いたウイルス複製阻害薬の評価
2.3 呼吸器オルガノイドを用いた治療薬スクリーニング
3 呼吸器オルガノイドを用いたインフルエンザ研究
4 呼吸器オルガノイドを用いたRSウイルス感染症研究
5 おわりに
参考文献
第4章 疾患特異的iPS細胞由来オルガノイドを用いた研究 林 洋平
1 疾患特異的iPS細胞
2 創薬研究に利活用される疾患特異的iPS細胞のバンキング
2.1 日本における疾患iPS細胞バンキング
2.2 世界の研究用iPS細胞バンキング
3 疾患iPS細胞が利用される創薬開発プロセス
4 疾患iPS細胞を用いた創薬開発の特色
4.1 動物実験代替法としての利点
4.2多 様な組織のモデル開発
4.3 細胞株としての安定的,永続的供給
5 疾患iPS細胞が利活用される領域
6 疾患特異的iPS細胞由来オルガノイド
7 疾患特異的iPS細胞由来オルガノイドを用いた研究例
7.1 若年性ネフロン癆に対する腎臓オルガノイドを用いた研究の背景
7.2 若年性ネフロン癆に対する腎臓オルガノイドを用いた病態モデル開発
7.3 若年性ネフロン癆に対する腎臓オルガノイドを用いた研究の展望
8 今後の課題と展望
8.1 均質な疾患iPS細胞を短期間に作製する手法
8.2 均質なオルガノイドを作製する手法
8.3 MPS(MicroPhysiological Systems)などを用いた高度化
8.4 単一遺伝疾患以外への適用拡大と遺伝子多型を考慮した臨床開発への展開
8.5 ゲノム編集技術,遺伝子治療技術の適用
参考文献
第5章 iPS細胞由来ヒト呼吸器オルガノイドを用いた創薬 山本佑樹
1 呼吸器疾患創薬の問題点
2 呼吸器オルガノイド研究の発展
3 iPS細胞由来呼吸器オルガノイドの疾患研究と創薬への応用
3.1 肺線維症
3.2 嚢胞性線維症・原発性線毛運動不全症
3.3 ウイルス感染症
3.4 薬剤性肺障害
4 iPS細胞由来呼吸器オルガノイド創薬応用の新たな展開
参考文献
第4編 MPS
総括:創薬におけるMPS・MEAの現状と展望 古江美保
第1章 MPS研究開発とレギュラトリーサイエンス 山崎大樹,石田誠
1 はじめに
2 MPSに関する欧米の規制当局の動向
2.1 米国・FDA(Food and Drug Agency)
2.2 ヨーロッパ・EMA(European Medicines Agency)
2.3 OECD Guideline for Testing of Chemicals, Section4
3 MPSに関する国内動向
3.1 AMED-MPS1
3.2 AMED-MPS2
3.3 MPS-RS
4 まとめ
参考文献
第2章 産業界におけるMPS利用の現状と課題 奈良岡 準
1 産業界を取り巻く環境
2 国内産業界の現状
3 国内産業系のコンソーシアム活動
4 産業界からMPSへの期待
5 MPS利用における課題
6 今後の展望
謝辞
参考文献
第3章 製薬企業における毒性評価での利用 荒木徹朗
1 製薬企業における毒性評価とは
2 MPSを医薬品の毒性評価で用いた事例
2.1 肝臓
2.2 腎臓
2.3 心臓
2.4 肺・呼吸器系
2.5 骨髄・造血系
2.6 消化管
3 In vitro試験系におけるCoU拡大とQualificationの課題
参考文献
第4章 製薬企業における薬物動態評価でのMPS活用 今岡知己
1 はじめに
2 消化管吸収評価におけるMPSアプリケーション
3 肝臓クリアランス評価におけるMPSアプリケーション
4 CNS・脳移行性評価におけるMPSアプリケーション
5 腎排泄におけるMPSアプリケーション
6 今後の展望
参考文献
第5章 薬効薬理モデルとしてのMPS 清田泰次郎
1 はじめに
2 MPSの使用方法とMPSの撮影
3 撮影対象となるプロセスとMPS分類
4 撮影方法と撮像プラットフォーム
5 MPSデバイスの撮像例
6 まとめ
参考文献
広告1 培養最適化支援ソフトウエア CellTune株式会社島津製作所
広告2 創薬研究用ヒト腎細胞3D-RPTEC® オリエンタル酵母工業株式会社
第5編 MEA
第1章 in vitro神経ネットワークにおけるMEA研究 鈴木郁郎
1 はじめに
2 in vivoへの外挿性を有する医薬品の痙攣毒性予測
3 UHD-CMOS-MEA
4 おわりに
参考文献
第2章 製薬企業におけるMEA技術の安全性評価への利活用 宮本憲優
1 はじめに
2 安全性に関わるMEA技術の製薬企業間のコラボレーション
3 おわりに
参考文献
広告3 高密度微小電極アレイ(HD-MEAプラットフォーム)MaxWell BIOSYSTEMS
第6編 自動化
総括:自動化 神田元紀
第1章 ラボラトリーオートメーションの基礎 神田元紀,加藤 月
1 はじめに
2 ラボラトリーオートメーションとは
3 ラボラトリーオートメーションとファクトリーオートメーション
4 機械化・自動化・自律化
5 典型的な活用用途
5.1 スクリーニング
5.2 細胞製造
5.3 データ解析
6 代表的な研究開発事例
6.1 Adam/Eve/Genesis
6.2 RIPPS
6.3 ヒューマノイドロボット
6.4 LabDroid「まほろ」
6.5 自律実験
7 実験の自動化から研究室の自動化へ
8 研究室の自動化のためのソフトウェア開発
9 コミュニティ
9.1 SLAS
9.2 SiLA
9.3 ノーベルチューリングチャレンジ
9.4 Acceleration Consortium
9.5 スクリーニング学研究会
9.6 ラボラトリーオートメーション協会
10 人間とロボットの新しい関係へ
11 おわりに
参考文献
第2章 細胞創薬自動化プラットフォーム「Mahol-A-Ba(まほろば)」 生田目一寿
1 背景
1.1 創薬トレンドについて
1.2 PS細胞創薬を志向した自動化機器導入の背景
2 Mahol-A-Baの紹介
2.1 「まほろ」
2.2 「スクリーニングステーション」
3 Mahol-A-Baの遠隔操作
4 Mahol-A-Ba間のプログラムを介した技術移管
5 おわりに
謝辞
参考文献
第3章 新薬創出を推進するラボオートメーションの取り組み 須山英悟
1 はじめに
2 サンプル保管・管理自動化
3 低分子化合物スクリーニングの自動化
4 実験データ解析の自動化
5 ARP作成の集約実施
6 実験装置拡張カスタムパーツ内製
7 今後の展望
参考文献
第4章 創薬研究における実験と細胞培養の自動化 浅野秀光
1 はじめに
2 実験自動化の検討
2.1 実験手順の分析
2.2 自動化スコアの分析
2.3 要求仕様の策定
3 自動化システムの開発
3.1 機器の選定
3.2 ラボウェア搬送機の選定
3.3 スケジュールソフトウェアの選定
4 細胞培養の自動化
4.1 細胞培養の課題
4.2 細胞培養自動化のメリット
4.3 細胞培養自動化の留意点
4.4 細胞培養自動化システムの紹介
5 おわりに
参考文献
第5章 創薬研究における自動培養装置の現状と展望 八木健介
1 はじめに
2 当社(マイクロニクス株式会社)の紹介と自動培養装置の導入実績
3 自動培養装置の技術概要
4 製薬会社への導入実績と主な特徴
5 当社が直面した課題とその解決策
5.1 システム全体における課題と解決策
5.2 各工程における課題と解決策
6 自動培養装置の今後の展望
第6章 汎用ヒト型ロボットLabDroid「まほろ」 松熊研司
1 はじめに
2 システム構成
3 設計思想
4 「まほろ」の価値とは
5 おわりに
第7章 テカンにおける自動分注機を用いた創薬ソリューション 伊藤浩孝
1 テカンジャパン株式会社の紹介
2 創薬・医薬品開発におけるラボラトリーオートメーションの有用性
3 テカンFluent®における創薬ソリューション
3.1 Fluentの特性
3.2 Fluentを用いたアプリケーション
3.2.1 スクリーニング
3.2.2 細胞ベースアッセイ
3.2.3 バイオマーカー検出
3.2.4 分子生物学アッセイ
3.2.5 プロテオミクス
3.2.6 薬物動態および薬力学(PK/PD)
4 おわりに
第7編 人材育成
総括:バイオ産業における人材育成 古江美保
第1章 バイオ産業における人材育成の課題─細胞培養の標準化と培養実習─ 古江美保
1 背景
2 細胞培養学
3 細胞培養の日本と欧米の教育の違い
4 細胞培養の標準化
4.1 Good Cell Culture PracticeとBestpractices in cell culture
4.2 細胞培養における基本原則の提案
5 理論の学習
6 理論と実践のギャップを埋める提案
6.1 操作の標準化
6.2 自動化技術からの学習
6.3 詳細なプロトコールの作成
6.4 細胞培養の定量的評価の導入
6.5 継続的な教育とトレーニング
6.6 フィードバックシステムの構築
7 細胞培養実習
8 学習用バーチャルラボ・学習ゲーム
9 まとめ
謝辞
参考文献
第2章 バイオ医薬領域における人材の能力可視化と人材育成 大政健史,桑原寿江
1 はじめに
1.1 バイオテクノロジー市場予測と各国の施策
1.2 人材戦略の変化(人材マネジメントの潮流)
1.3 バイオ医薬産業における人材育成と人材能力の可視化
2 技能・知識
2.1 技能の可視化
2.2 知識の可視化
3 行動特性
4 まとめ
参考文献
第3章 創薬研究におけるバイオ人材育成 CMC開発人材とGMP製造人材 内田和久
1 はじめに
2 バイオロジクス全体の歴史とプロセス4工程について
3 CMC人材とGMP人材
4 人材育成は単一業界の課題ではない
5 細胞医療・遺伝子治療の人材育成
6 VRの活用による人材育成とバイオDX人材の育成7まとめ
参考文献
第4章 GMP教育の課題と現状 髙屋敷均,鈴木雅寿,櫻井信豪
1 背景
2 「医薬品等品質・GMP講座」がめざすもの
3 GMP人材の不足の課題を解決するためには
3.1 欧州連合(EU)のQualified Person(QP)の教育
3.2 課題解決のために構築中のGMP教育訓練コース
3.2.1 E-ラーニング(e-GMP)
3.2.2 GMP対応エンジニアリング講座・GMP対応マネジメント講座
3.2.2.1 GMP対応エンジニアリング講座
3.2.2.2 GMP対応マネジメント講座
3.2.3 グループワーク
3.2.4 実技講座
3.2.4.1 環境管理
3.2.4.2 空調
3.2.4.3 有害生物管
3.2.4.4 無菌医薬品製造工程
3.2.5 実効性のある教育訓練のために
4 まとめ
第5章 バイオ実習シミュレータの開発 大沼清,古江美保
1 はじめに
2 開発の目的
3 開発方針
4 開発したアプリケーションの説明
4.1 フロントページ
4.2 実験ページ
4.3 学生・エンドユーザの学習方法4.4終了画面4.5管理ページ
5 授業結果
6 展望
参考文献
執筆者一覧(掲載順)
古江美保 (株)セルミミック 代表取締役
関野祐子 NPO法人 イノベーション創薬研究所 理事長
福角勇人 独立行政法人 国立病院機構大阪医療センター 臨床研究センター
先進医療研究開発部 幹細胞医療研究室 室員
金村米博 独立行政法人 国立病院機構大阪医療センター 臨床研究センター
臨床研究センター長
森本 悟 慶應義塾大学 殿町先端研究教育連携スクエア 慶応義塾大学再生医療
リサーチセンター 特任准教授/副センター長
河野岳生 京都大学(CiRA)iPS細胞研究所
小薮直生 京都大学(CiRA)iPS細胞研究所
近藤孝之 京都大学(CiRA)iPS細胞研究所 特定拠点講師,
国立研究開発法人 理化学研究所
バイオリソース研究センター(BRC)iPS創薬基盤開発チーム,
国立研究開発法人 理化学研究所
革新知能統合研究センター(AIP)iPS細胞連携医学的リスク回避チーム
井上治久 京都大学( CiRA)iPS細胞研究所 教授,
国立研究開発法人 理化学研究所
バイオリソース研究センター(BRC)iPS創薬基盤開発チーム,
国立研究開発法人 理化学研究所
革新知能統合研究センター(AIP)iPS細胞連携医学的リスク回避チーム
山元智史 国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部 研究員
石井明子 国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部 部長
吉岡祐亮 東京医科大学 医学総合研究所 講師
一木隆範 (株)イクストリーム 取締役
粂 昭苑 東京科学大学 生命理工学院 教授
白木伸明 東京科学大学 生命理工学院 准教授
乾 達也 大阪大学大学院 薬学研究科 特任研究員
水口裕之 大阪大学大学院 薬学研究科 教授
橋本里菜 京都大学 iPS細胞研究所 特定研究員
高山和雄 京都大学 iPS細胞研究所 講師
林 洋平 国立研究開発法人 理化学研究所 バイオリソース研究センター
iPS細胞高次特性解析開発チーム チームリーダー
山本佑樹 HiLung (株) 代表取締役
山崎大樹 国立医薬品食品衛生研究所 安全性生物試験研究センター 薬理部 室長
石田誠一 崇城大学 生物生命学部 生物生命学科 教授
奈良岡準 アステラス製薬(株)
非臨床バイオメディカルサイエンス探索病態生理研究室ヘッド
荒木徹朗 協和キリン(株) 研究本部 バイオ創薬センター
トランスレーショナルリサーチ研究所
安全性1グループ 主任 研究員
今岡知己 第一三共(株) 薬物動態研究所 主任研究員
大渕雅人 アステラス製薬(株) Universal Cells, Biology 主任研究員
清田 泰次郎 (株)ニコン ヘルスケア事業部 事業部付
鈴木郁郎 東北工業大学工学部 電気電子工学科 教授
宮本憲優 エーザイ(株) DHBL Biopharmaceutical Assessments(BA)
ファンクション高度バイオシグナル安全性評価部 主幹研究員
神田元紀 国立研究開発法人 理化学研究所 生命機能科学研究センター 上級研究員
加藤 月 国立研究開発法人 理化学研究所
生命機能科学研究センター 学振特別研究員 PD
生田目 一寿 アステラス製薬(株)
開発研究ディスカバリーインテリジェンスアドバイスモデリング&アッセイ
主管研究員
須山英悟 中外製薬(株) バイオロジー基盤研究部
創薬クロステックグループ 主席研究員
浅野秀光 ローツェライフサイエンス(株) 取締役
八木健介 マイクロニクス(株) 代表取締役社長
松熊研司 ロボティック・バイオロジー・インスティテュート(株) 代表取締役社長
伊藤浩孝 テカンジャパン(株) 代表取締役社長 兼 アジアパシフィック代表
大政健史 大阪大学大学院 工学研究科 教授
桑原寿江 大阪大学大学院 工学研究科 特任研究員
内田和久 神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科 特命教授
髙屋敷 均 東京理科大学 薬学部医薬品等品質・GMP 講座 エキスパート
鈴木雅寿 東京理科大学 研究推進機構 総合研究院 プロジェクト研究員
櫻井信豪 東京理科大学 薬学部医薬品等品質・GMP講座 教授